はじめに
37週になると正期産に入り、「いつ生まれても良い」と言われる時期になります。もうすぐ赤ちゃんに会えるという嬉しさとともに、「陣痛ってどうなんだろう?」「どういう感じでお産は始まるの?」と、緊張感や不安を抱く方も多い時期ではないでしょうか。
助産師である私自身も、期待と不安が入り混じる気持ちを抱えていました。
病院では入院の判断を日々してきた立場でしたが、いざ自分のこととなると、**お産が始まる前の“微妙な兆候”**や、「これって連絡していいのかな?」と迷う気持ちがとてもよく分かるようになりました。
今回は、1人目出産時に私に起きた兆候と入院までの流れを、助産師の視点も交えてまとめてみました。
これから出産を控えている方の参考になれば嬉しく思います。
私に起きたお産の兆候【1人目編】
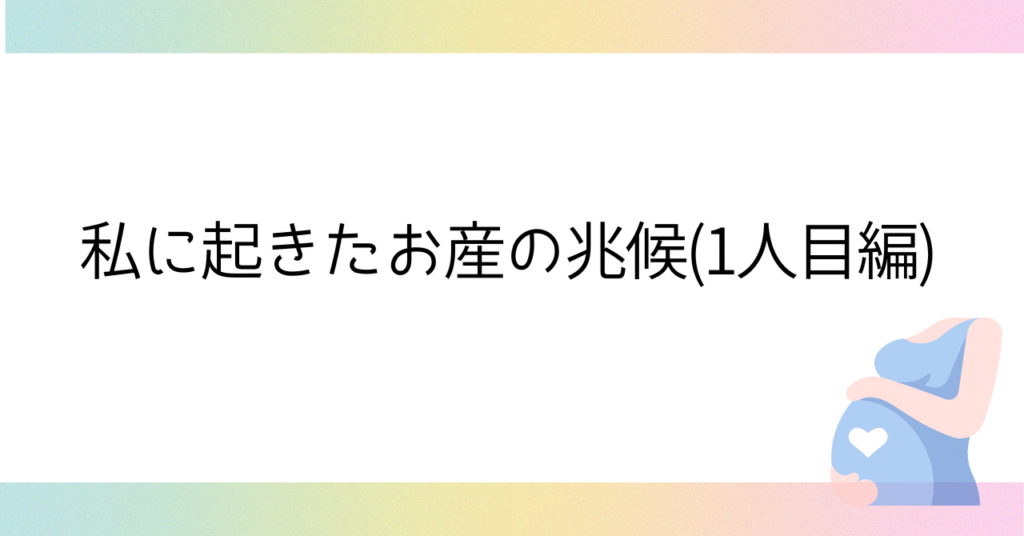
繰り返す前駆陣痛
1人目のときは、出産の1週間前から前駆陣痛が始まりました。特に夜から夜中にかけて、7〜10分間隔でお腹が張るような痛みがあり、それで目が覚めることも多くありました。
目が覚めては「間隔を測る → 少し寝る → また痛みで起きる」ということを繰り返していましたが、
朝7時ごろになると落ち着き、1時間に1回程度の軽い張りになって、痛みも感じなくなっていました。
出産3日前の変化と妊婦健診での対応
出産の3日前には、**少量の薄い茶色の出血(おしるし)**がありました。
その時点では量も増えず、色も薄かったため、次回の妊婦健診を待つことにしました。
健診では、前駆陣痛のことを医師に伝えたところ、内診で子宮口は1cmの開き。
その際、**卵膜剥離(らんまくはくり)**という方法で子宮口付近を少し刺激してもらいました。
刺激後、陣痛の間隔と痛みが急変!
卵膜剥離をしてもらった後、帰宅するまでの間に陣痛の間隔は5分おきに。
痛みも強くなり、歩くのがつらくなって立ち止まってしまうほどでした。
その後も2〜5分間隔で強めの痛みが続きましたが、
赤いドロッとした出血(本格的なおしるし)が見られなかったため、
「まだ進んでいないかも」と思いながらも、そのまま自宅で3時間様子をみていました。
病院へ連絡と受診、そして入院へ
3時間後、痛みの間隔が変わらず続いていたため、再度病院に電話し受診しました。
診察の結果、午前中の健診時と同じく子宮口は1cmでしたが、
モニターで見ると2〜3分間隔でお腹の張りがある状態でした。
この時点ではすぐの入院とはならず、
「2時間ほど院内で様子を見て、子宮口が進めば入院」という判断に。
待機中も痛みはどんどん強くなり、赤いドロッとした出血も出てきたため、お産が進んできたと思っていたら、
2時間後の内診では子宮口3cmに開いており、そこで正式に入院となりました。
助産師としてみてきた「お産の兆候」と「入院のタイミング」
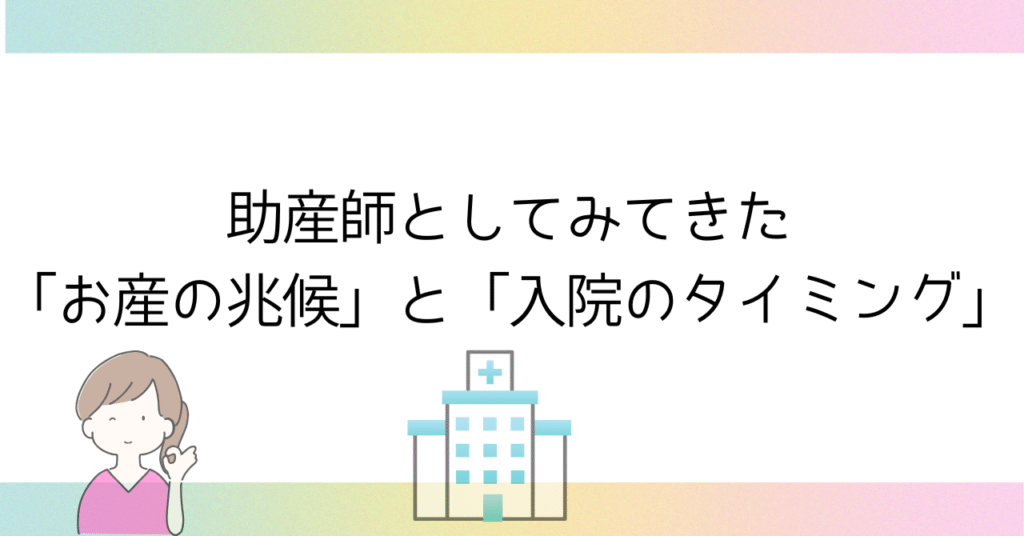
お産の始まり方は人それぞれで、いくつかのパターンがあります。
たとえば、
- 陣痛から始まる
- 破水から始まる
- 出血(おしるし)から始まる
といったさまざまなケースがあります。
また、赤ちゃんの頭が下がってくることで、
- 胃の不快感が軽くなる(胃がスッキリする)
- お通じがよくなる
といった変化を感じる方もいます。
私の病院での入院目安
病院によって入院基準は異なりますが、私が勤務していた病院では、以下のような目安で初めてのお産の方(初産・1人目)は入院をお願いしていました:
✅ 陣痛がある場合
- 陣痛が約5分間隔になってきたとき
- 子宮口が3cm程度以上になってきたとき
- 赤いドロッとしたおりもの(血性のおりもの)が出てきている
✅ 破水の可能性がある場合
- 破水感があれば、昼夜問わず来院
- 検査で陽性なら必ず入院
ただし、尿漏れ・入浴後のお湯漏れ・おりものの増加など、破水かどうか判断しにくいこともよくあります。
そのような場合、特に夜間など診察時間外では、清潔なパッドを当てて1時間ほど様子をみていただき、必要であれば受診の判断をしてもらっていました。
ただし、この内容は初産(1人目・初めての出産さんの基準であり、経産婦(2人目以降の出産)の方には入院のタイミングが異なりますので注意してください。
経産婦さんの入院目安についてはまたの機会にご紹介したいと思います。
お産は人それぞれ。迷ったら相談を
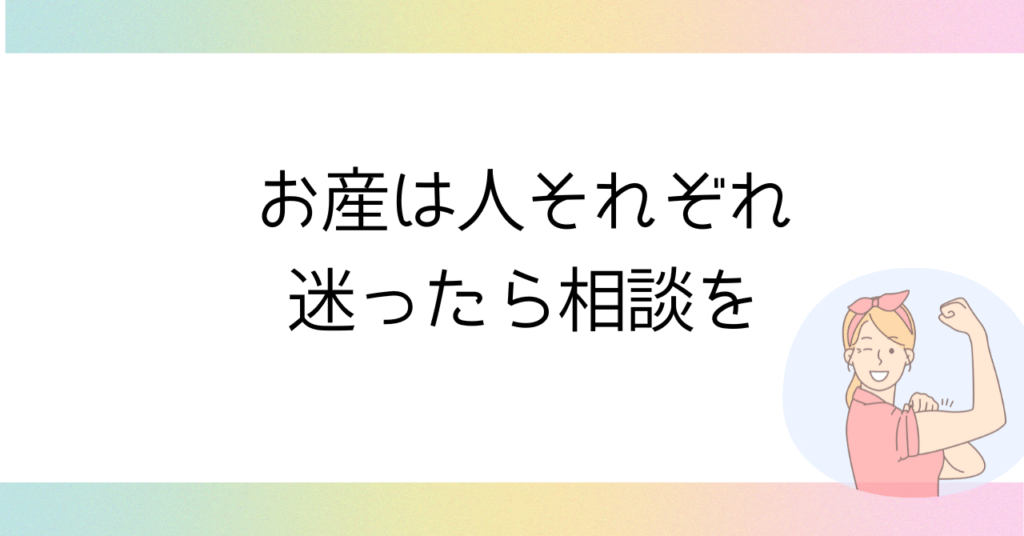
お産の兆候は本当にさまざまです。
「これって本陣痛?」「今連絡していいのかな?」と迷う方も多いですが、不安なときは、遠慮せずに病院に連絡・相談することが何より大切です。
余談ではありますがお産を進める秘訣はいろいろありその中に、陣痛を気にしすぎないこともあると思っています。陣痛があっても陣痛がない間にウトウトして眠くなるなら他のことしないでウトウトしたり眠ることはすごく大切です。
私自身、助産師でありながら、自分の出産では不安や迷いがたくさんありました。
だからこそ、この記事がこれから出産を迎える方の安心材料のひとつになればうれしいです。
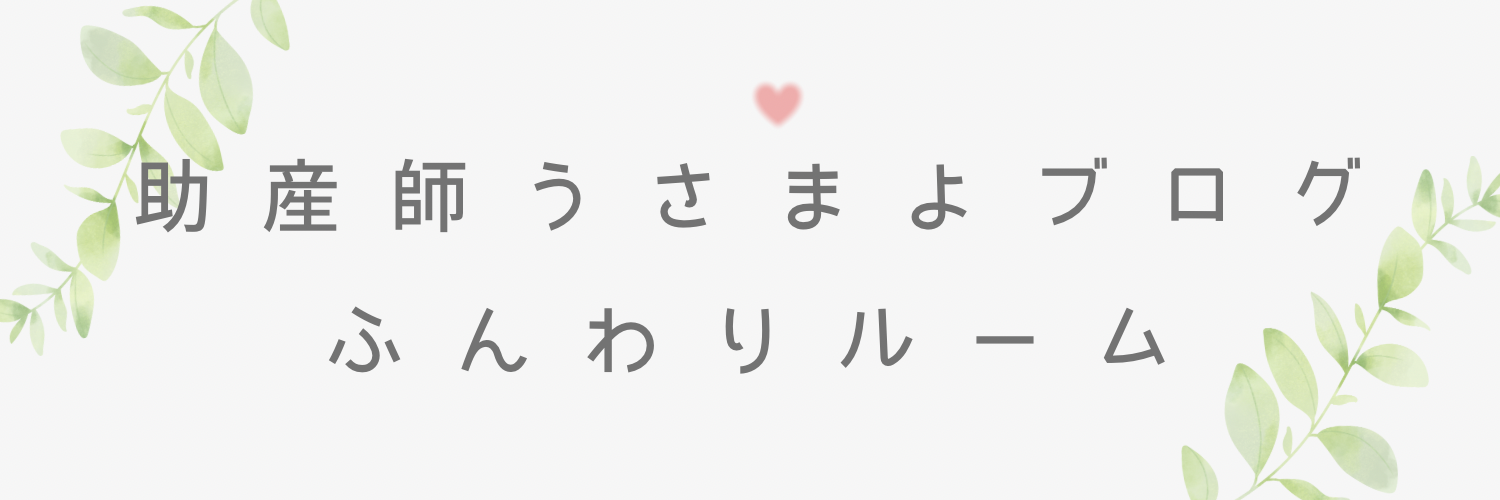
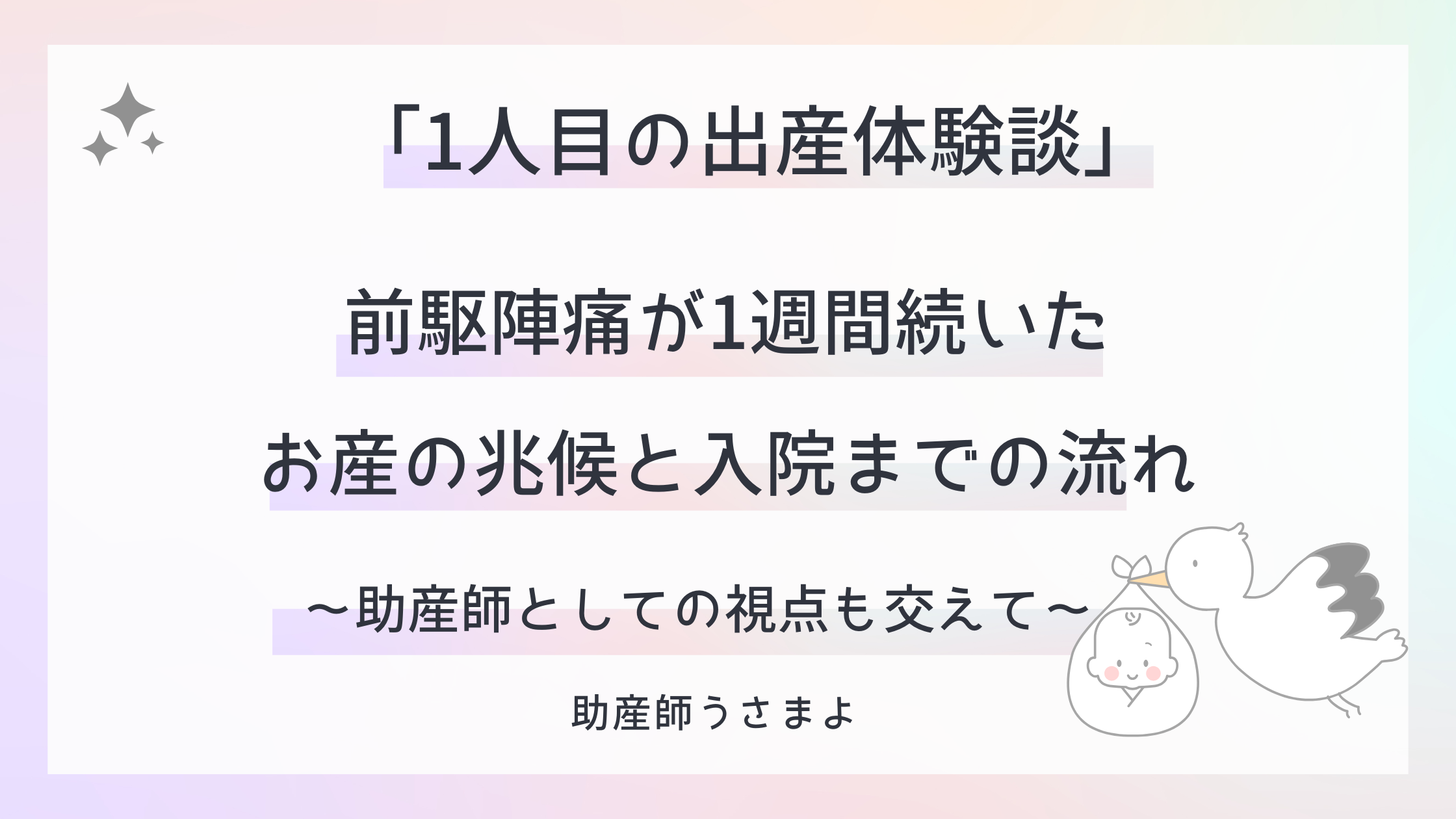
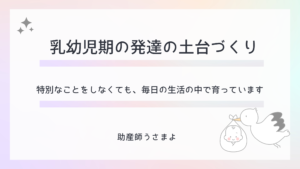
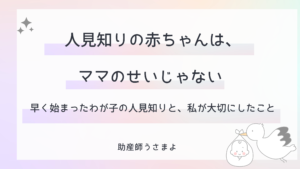
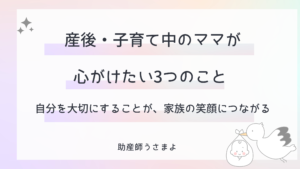
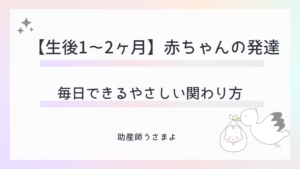
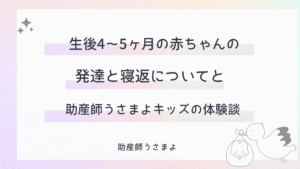
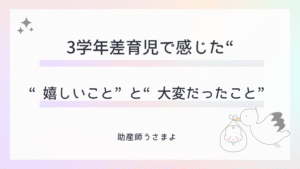
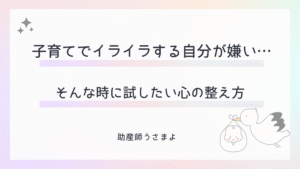
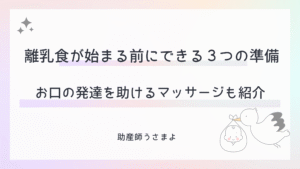
コメント