こんにちは。助産師として多くの赤ちゃんと関わってきた私ですが、自分の子育てとなるとまた違った難しさに直面しました。
今日は**「繊細で敏感な赤ちゃんのねんね」**について、私自身の経験を交えながらお話しします。
我が子は繊細で敏感なタイプでした
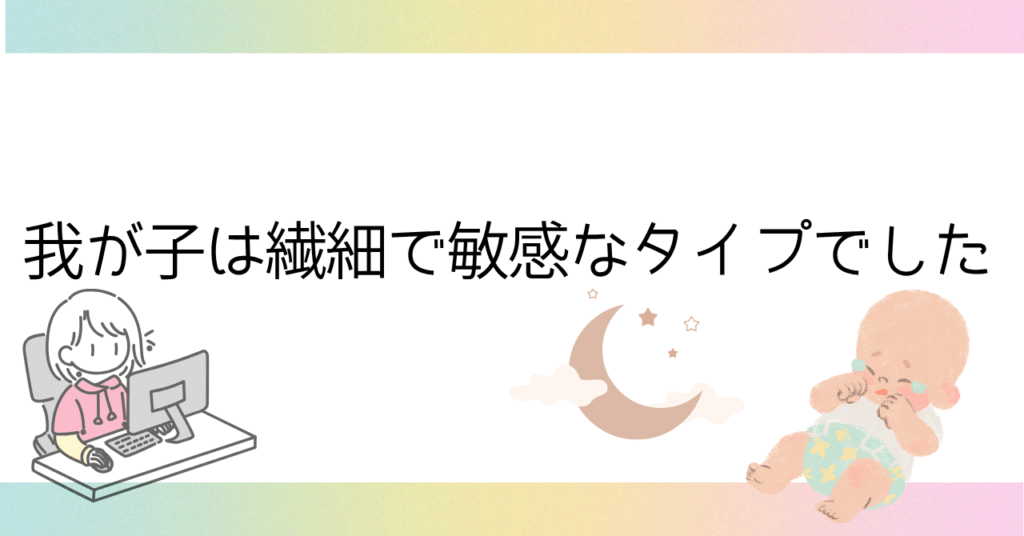
上の子は、生まれた頃からとても繊細で敏感な子でした。例えば背中スイッチ、場所見知りや人見知りが激しく生後5か月の時は私以外の抱っこで寝れず、抱っこを夫に交代すると癇癪になるため代わることもできないなどなど…4歳になった時でも、夜寝る前に「怖い」と不安を感じると抱っこして欲しいということがあります。
今振り返ると、赤ちゃんの頃は慣れない刺激や環境の変化に対して、不安や不快感、恐怖を強く感じていたのではないかと思います。
ねんね苦労〜置いた瞬間に泣く日々〜
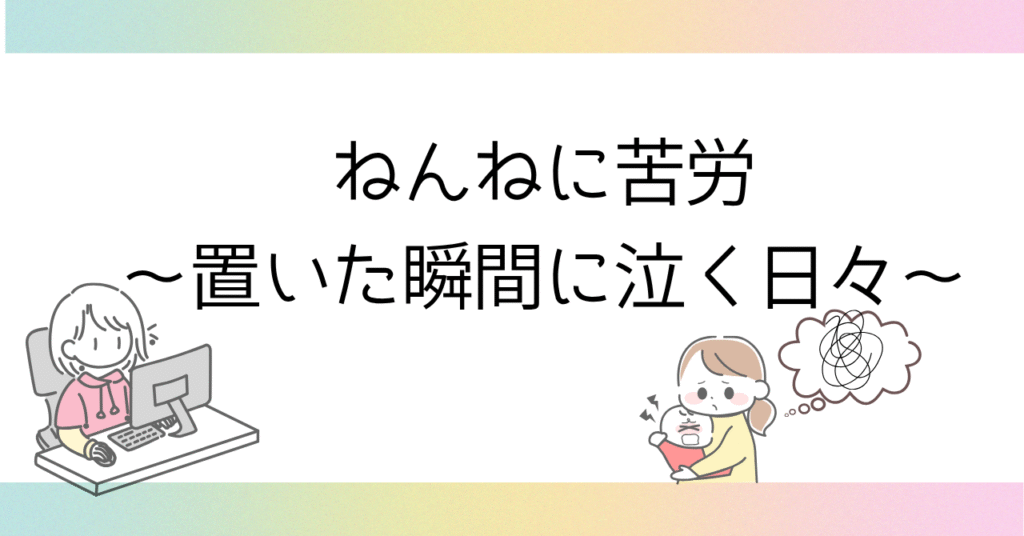
いわゆる“背中スイッチ”はもちろんありました。
授乳や抱っこで寝かしつけて深く眠っていても、布団に置くと起きてしまい泣く…。それが毎日でした。
自宅の布団でも置けないこともあれば、実家への帰省や旅行では特に大変で、ほとんど寝られなかった夜もあります。
ネントレ(ねんねトレーニング)を試してみたけど
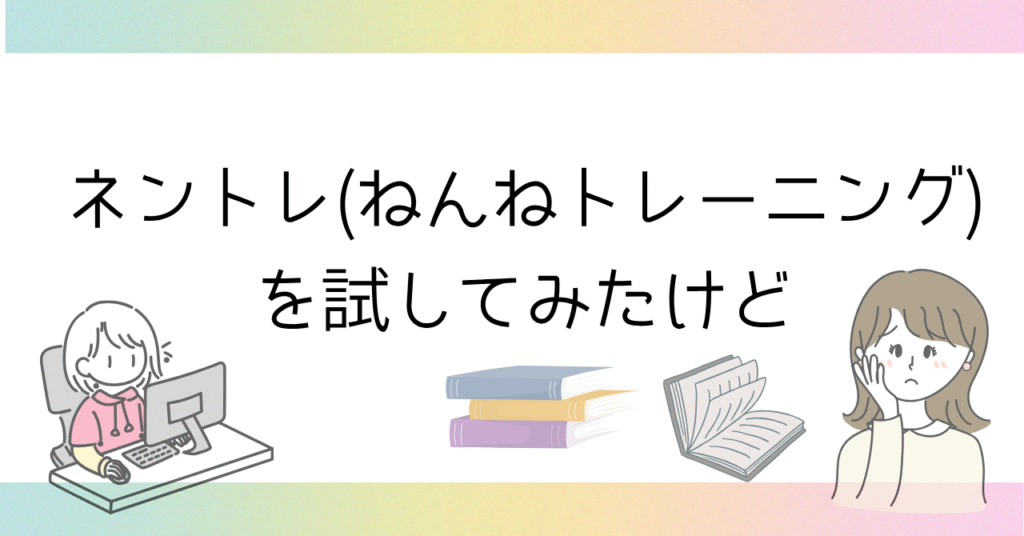
ネントレの本を何冊も読み、環境づくりなどを工夫してみました。
眠りの誘うような環境づくりの工夫はとても参考になるものばかりでした。部屋の温度や照明、ねんねのリズム・生活リズムを整えるなどなどたくさん取り入れて見ました。でも私自身、泣き続ける我が子を見守ることが辛く、向いていないと感じたんです。そのためネントレは諦めました。
それでも試してよかった「ねんねサポート法」
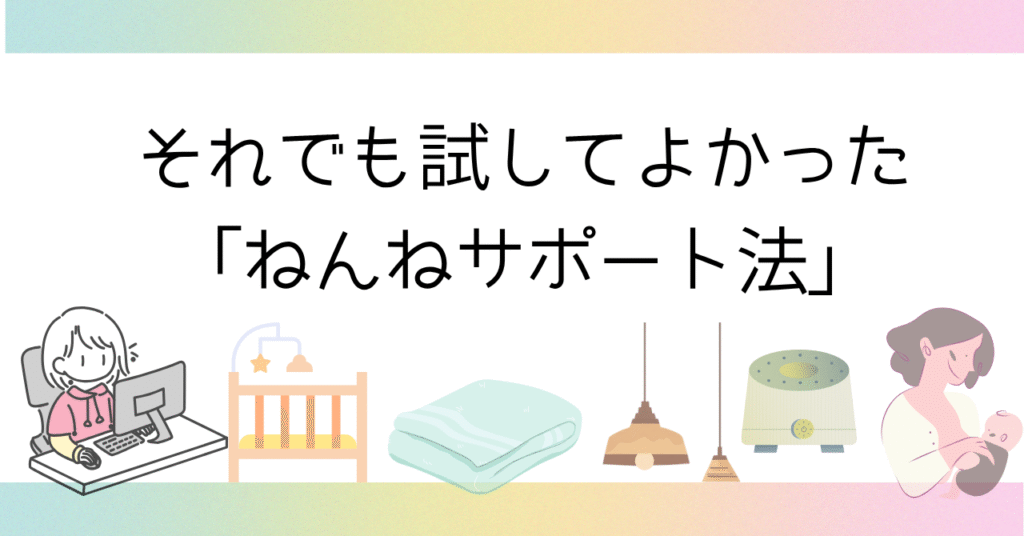
そんな中でも、実際に効果があった・役立った方法をご紹介します。中にはネントレから考えた独自の方法もあります。
すべてが万人向けではないかもしれませんが、「うちの子にも試してみたい」と思えるものがあれば嬉しいです。
①授乳クッション+バスタオル作戦
授乳クッションの上にバスタオルを敷き、赤ちゃんが寝たらそのままバスタオルごと布団に移動。
温度・感触が変わらず安心しやすかったのか、置いても起きにくかったです。
②抱っこ→布団への移行時は「Cカーブ」+お腹に手を当てる
・Cカーブ(丸い姿勢)を意識して抱っこ
・布団に置く直前・直後にお腹に手を当てる(安心感UP)
置く時Cカーブを意識して置くきます。すると置いた時に瞬間の“ビクッ”を防ぐ・もしくは“ビクッ”となってもすぐ眠りについてくれる事が多く効果的でした。
③いつもの寝具を持ち歩く
旅行や帰省の際は、**普段使っている寝具(シーツ・タオル・掛け物など)**を持っていきました。
いつもと同じにおいや肌触りが同じだと、少し安心するようでした。
④暗さの調整(真っ暗=怖い子もいる)
我が子は暗すぎると大泣きするタイプだったので、部屋の明るさは少しずつ調整。
・お昼寝はカーテンで遮光
・漏れる光が気にならないように工夫
・「どのくらいの暗さが落ち着くか」も試しながら探りました
⑤寝かしつけ用の音楽を決める
1つの音楽を寝かしつけの時だけに使い、「この曲=ねんねの時間」と体で覚えてもらう作戦。
すぐには効果が出ませんでしたが、2〜3歳頃にはその音楽をかけると眠気が訪れるように!
【番外編】ホワイトノイズも使用しました
ホワイトノイズ(ザーッという音)を使っていた時期もありました。
我が子はこれで眠りやすくなるタイプではなかったのですが、寝た後にちょっとした物音で起きにくくなる効果があり、生活音対策に◎。
赤ちゃんにも「個性」あると実感
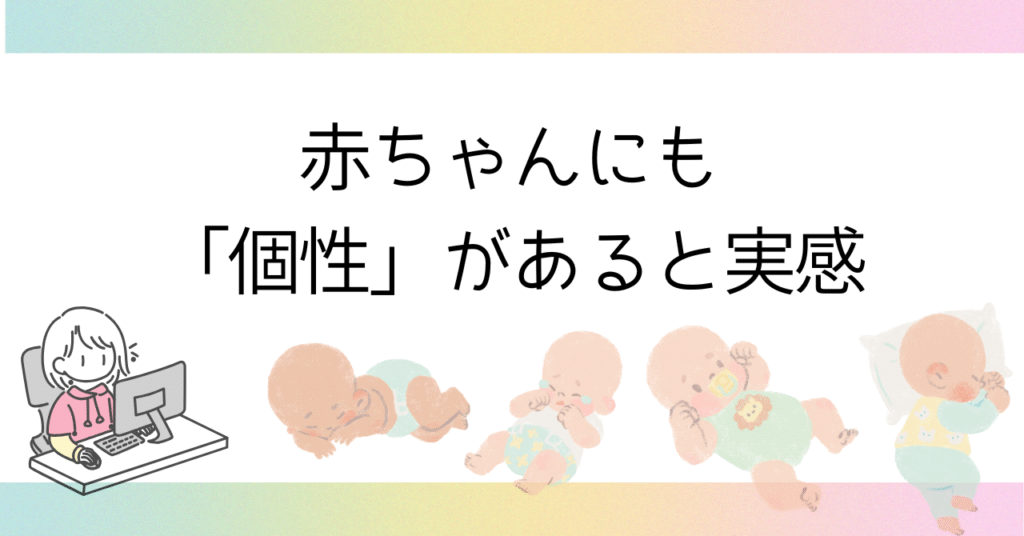
助産師として新生児室でたくさんの赤ちゃんを見てきましたが、眠ることについてだけでも
- すぐに1人で寝る子
- 抱っこしていないと泣き続ける子
- 昼夜逆転している子
- ママの抱っこでは泣いていても、新生児室に来ると落ち着き寝る子
本当にさまざまです。
そして我が子は**「自分で寝ていくことが苦手なタイプ」**だったのだと思います。
自分と赤ちゃん、両方に合う方法を
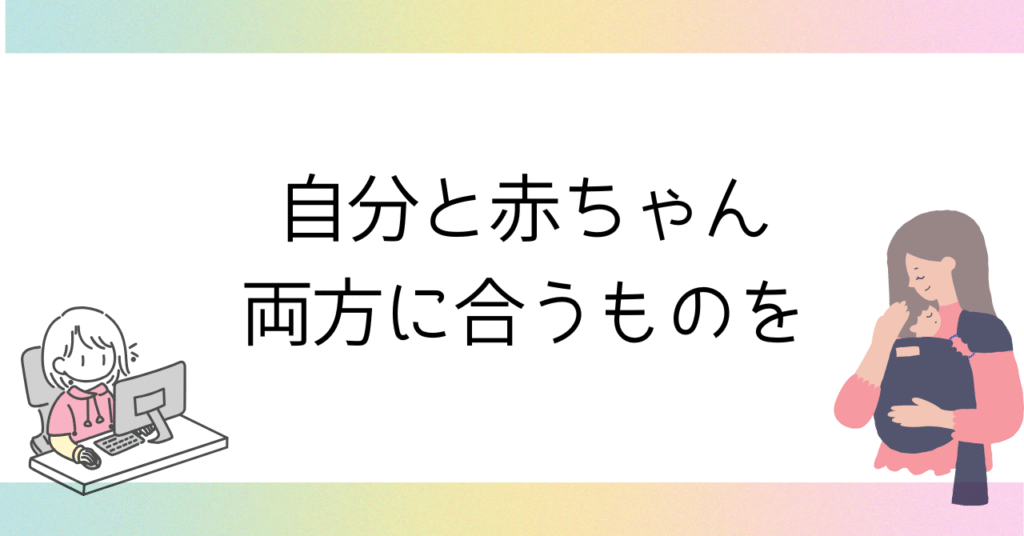
「こうするといい」という情報はたくさんあります。
でもそれが 「赤ちゃんのタイプに合うか」、**「親の性格や考え方にも無理がないか」**がとても大切です。
私は、**「抱っこで落ち着くなら、できる範囲で抱っこしてあげたい」**と思っていました。
体力もあったので、抱っこや授乳での寝かしつけがメインになりました。
最後に
今回ご紹介した内容が、みなさんのお子さんにも当てはまるとは限りません。
それでも、「我が子に合う方法を探してあげたい」という気持ちのヒントになればうれしく思います。
どんな方法でも、親子が安心できることが一番。
一緒に頑張っていきましょう。
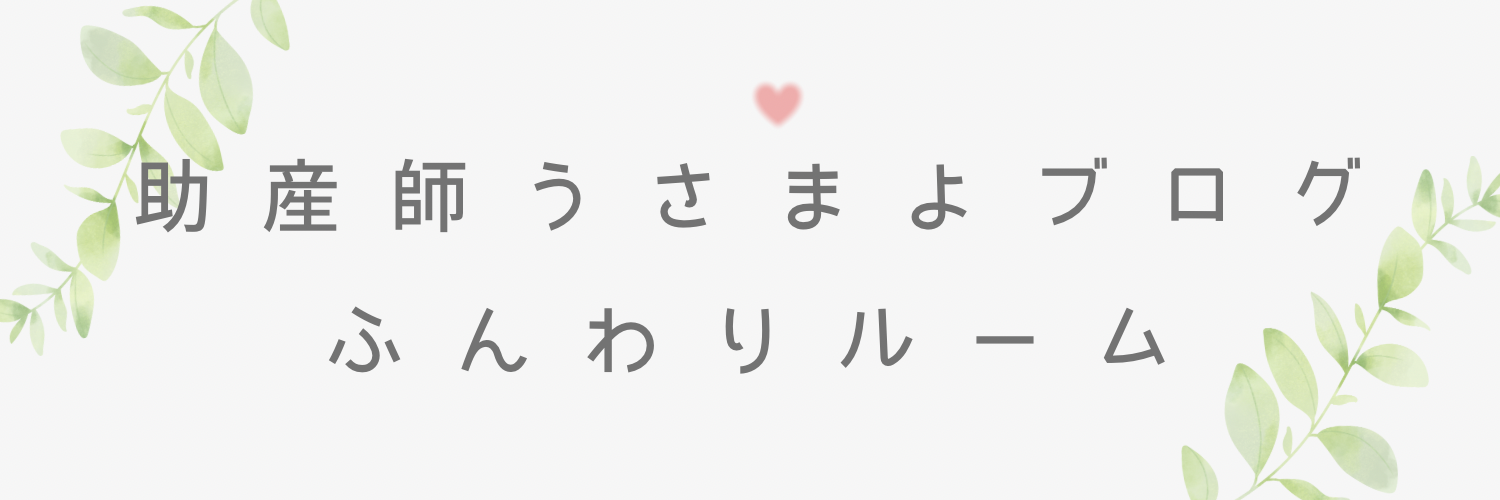
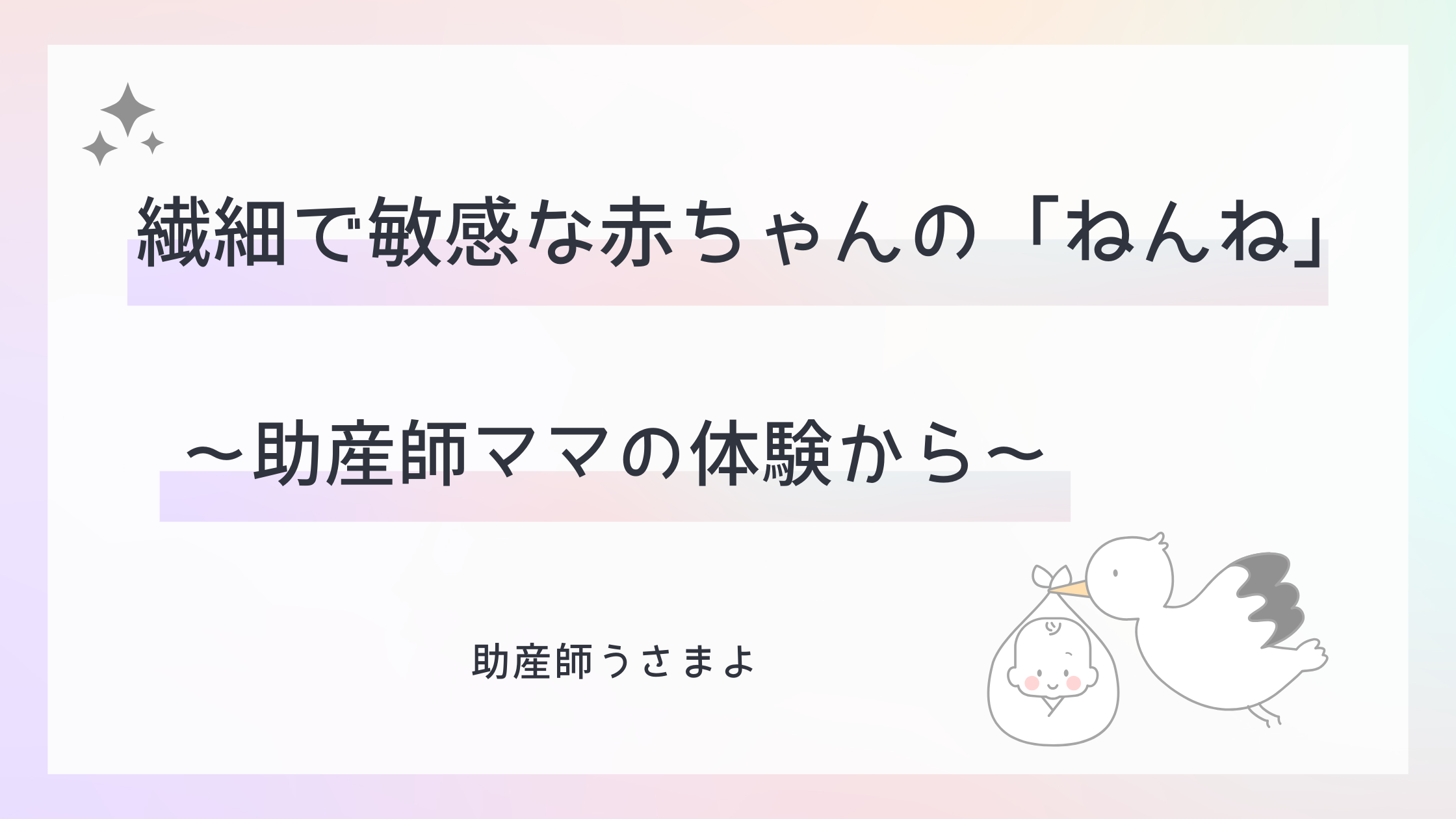
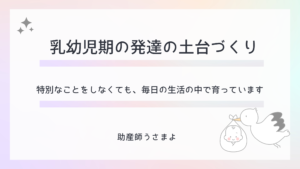
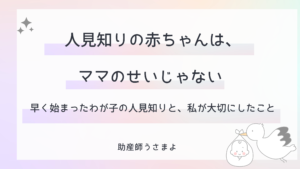
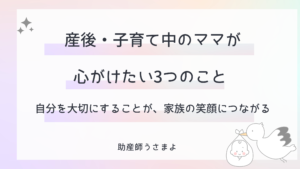
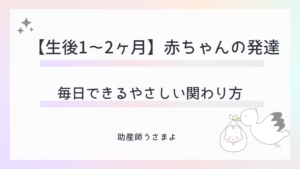
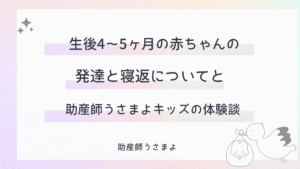
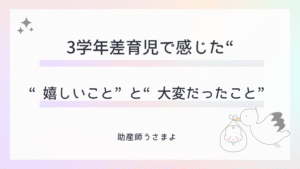
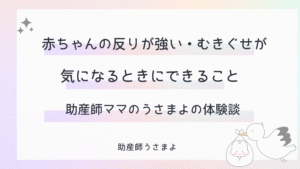
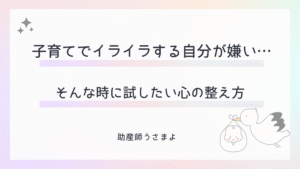
コメント